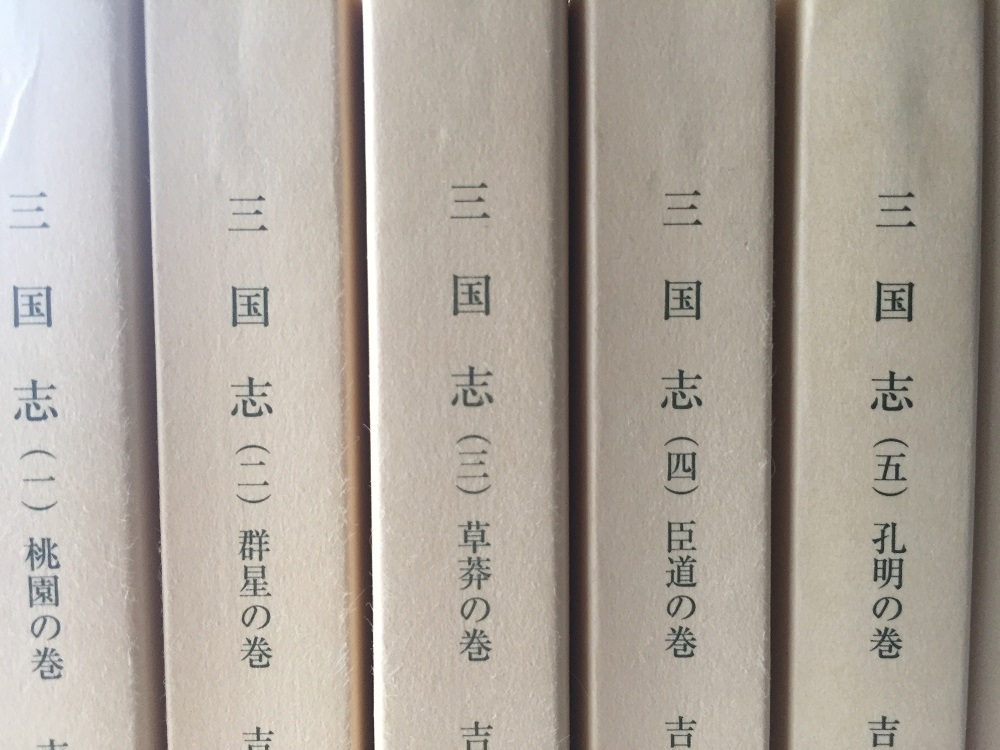内容
近年、漢中(かんちゅう)の民のあいだを、五斗米教(ごとべいきょう)と呼ばれる宗教が風靡していた。漢中におけるその勢力は国主をしのぐものであった。
教主は、師君(しくん)と称し、名を張魯(ちょうろ)といった。
教養なく、明日の希望もない民衆は、「これこそ天来の道士様」と、五斗米をかついで、救いを求めた。
けが人や病人が祈祷をたのむと、時々、奇跡が生まれ、完治する者がでる。それで、愚民は信じてしまうのだ。
邪教の蔓延は、今年で三十年にもなるが、中央から遠い巴蜀(はしょく)の地であるため、兵を向けて一掃することもできなかった。
そこで、教主張魯に対して、鎮南中郎将(ちんなんちゅうろうしょう)という官職を与えて、漢寧(かんねい)の太守(たいしゅ)に封じ、そのかわりに、年々の貢ぎ物を差し出すようにと誓わせていた。
つい最近のこと、漢中で、ある百姓が自分の畑から黄金の玉璽(ぎょくじ)を掘り出した。
百姓が庁へ届けると、「天が、漢寧王(かんねいおう)の位につくべし、と師君へ授けられたもの」と張魯の群臣は言い、張魯に王位につくことをすすめた。
閻圃(えんほ)という者は「我らは、蜀四十一州を併合統一した後に、曹操に当るのが、正しくないかと考えられます」と進言した。
張魯(ちょうろ)の弟である張衛(ちょうえい)も同意し、「蜀を加え、武甲と仁政をもって統治したうえで、帝王になられれば、これこそ千年の基業を開くことができるに違いない。不肖張衛に、入蜀の兵馬を授けてください」と張魯に言った。
張魯はふたりの意見に心を動かされ、「準備にかかれ」と命じた。
蜀の交通の不便さは言語に絶するものがある。北方へ出るには剣閣(けんかく)のけわしい道を越えねばならず、南は巴山山脈(はざんさんみゃく)にさえぎられ、関中(かんちゅう)に出る四道、巴蜀へ通ずる三道も高くてけわしく、谷間に橋をかけ、大きな岩にすがりついて登っていかなければならなかった。それゆえ、蜀に敵が攻めてくることもなかった。
蜀の劉璋(りゅうしょう)は、父劉焉(りゅうえん)のあとを継いだが、国の平和に慣れて、遊んでばかりの暗君であった。
「漢中の張魯が攻めてくる。ああ、どうしたらいいか」劉璋は生まれて初めて、隣に敵がいたことを知った。
評議の席で、張松(ちょうしょう)という者が、立って発言した。「それがし、三寸の舌をうごかして、張魯の軍勢を退けてみせる」
「いかなる自信があって、そのような大言を吐くのか」劉璋は問うた。
張松は、許都に上って、曹操(そうそう)に会い、この禍いを変じて、蜀の大幸として見せると言い、大方策を発表した。
張松の献策は用いられることとなり、張松は都へ行くこととなった。旅行の準備と同時に、自分の家に画工を雇い、西蜀四十一州の地図を、精密に写させていた。
その地図は五十日ほどを要して、完成した。
張松は劉璋に出発の準備が整ったことを報告した。
劉璋は金珠(きんしゅ)錦繍(きんしゅう)の贈物を、白馬七頭に積んで、張松に託した。もちろん、曹操への礼物である。
張松は、都の旅館に落ち着き、拝謁簿(はいえつぼ)に姓氏官職などを記録し、連絡がくるのを待った。
しかし、幾日経っても、相府からの連絡がない。
旅亭の館主は、吏員に賄賂を贈らなかっったからだと、注意してくれた。
そこで、、客舎の主人から莫大な賄賂を相府の吏員に贈ると、五日目ごろに連絡があり、張松は、曹操に会うことができた。
曹操は張松をひとにらみすると、「蜀はなぜ毎年の貢ぎ物を献じないか」と責めた。
「蜀道は、盗賊の害が多く、貢ぎを送る方法がありません」
「予は天下を治めておる。なんで、交通の要路に野盗乱賊が出没しようか」
「決してまだ天下は平定しておりません。漢中に張魯(ちょうろ)、荊州(けんしゅう)に劉備(りゅうび)、江南(こうなん)に孫権(そんけん)がおります」
曹操は席を立ち、後閣へ入っていった。
階下に整列していた近臣は、張松の愚を笑った。「はるばる参りながら、あえて丞相に逆らうとは。早く蜀へ帰りなさい」
張松は「ふふふ」ともらした。「さてさて、魏の人は嘘で固めているとみえる。わが蜀には、こびへつらうような者はいない」
「だまれ。魏人はこびへつらっているというのか」諸人のうちから、楊修(ようしゅう)という青年が、張松の前へ立った。
「すこし君に申しておきたいことがあるから、僕に従ってこっちへきなさい」と言い、楊修は張松を閣の書院へひっぱって行った。
関連記事